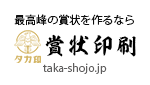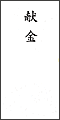キリスト教(カトリック):前夜祭・葬送式
前夜祭
個人の信仰に重きをおき、教会の教義を重んじるカトリック教(旧派)における葬祭の儀式は大変重要視され行われます。
前夜祭では自宅で行う場合と教会を借りて行う場合があり、司祭の神父によって聖油の秘跡・納棺式・前夜祭の順で挙行され、聖書朗読・祈り・説教・賛美歌合唱・献花などが行われます。
式後のおもてなし
仏式の通夜の場合と違って通夜振る舞いなるものは行われませんが、通夜祭の終了後に簡単な茶菓子程度で茶話会を用意して、故人の在りし日を偲び、思い出話などを語り合ったりします。
夜伽(よとぎ)
キリスト教では仏教などでいう夜伽という慣習はありませんが、故人の棺を安置する教会ではローソクを絶やさず灯火し、自宅でも棺に添えられたローソクの火を絶やさないようにします。
葬送式
カトリック教の弔い儀式である葬送式は教会で行われるのが基本で、故人の棺は教会の祭壇に安置され、棺やその周辺を多くの花で飾り付けられます。
儀式では、仏教の読経・神道の祭詞にかえて聖書の朗読、焼香・玉串奉奠にかえて献花を行うなど、キリスト教本来の儀式が踏襲されている一方で、日本の生活習慣に溶け込んだ日本独特の弔い様式が混在しています。それは仏教と神道が互いに影響しあって存在してきたのと同様に、日本におけるキリスト教布教の歴史の中にあって、古くから存在する日本の生活習慣の中に取り入れられる過程において、形成されていったものと考えられます。
カトリック教における告別式は、神を讃美し、故人の霊魂の永遠なる安やぎと幸を祈って神の身元に導くために営む儀式ですが、ミサ聖祭式・赦祷式・告別式と続き、安息のミサ・追悼説教・聖歌合唱・祝別(聖水・散香)・献花などが行われます。キリスト教では本来土葬による埋葬式が行われますが、日本においては他の宗教と同様に火葬による骨上げ(火葬式)を行います。 現在では、土葬による埋葬から火葬に変って、参列者が墓地まで行く機会がなくなるなど葬儀の慣習が変ってきたことから、葬儀と告別式を同時に行うのが一般的になり、告別式参列者も焼香による会葬をもって故人とお別れする形式に変ってきています。
ひとくちMEMO
- 宗教・宗派にかかわらず通夜・葬儀の儀式においては、町内会役員・近隣者・会社や職場や業界関係者・寺院や教会などの方々には、世話役・進行係・会計係・受付係・会場案内係・台所係・駐車及び交通整理係・霊柩車やハイヤー及びタクシーやマイクロバスの運転手・火葬場係員などの他、寺院のお手伝いさん・教会の聖歌隊やオルガニストなどとしてお世話になりますが、そうした方々への謝礼の献辞(表書き)は「御礼」とします。
(注:係員が公的職員の場合は謝礼受取りを禁じています。) - お祝い返しや香奠返しは通常1/2~1/3返しとされていますが、基本的には「上に薄く下に厚く」返すのが一般的とされています。また、商品で返す場合は1/3返し、商品券で返す場合は1/2返し、両方の場合は各々1/3返しが最近の傾向です。
- 蓮の絵が入ったものは佛式用に付き、藍銀水引ののし袋・のし紙は蓮の絵が入っていないものを用いる。
- 香奠返しは前夜祭・葬送式時にはお印程度のものを手渡し、正式にはミサ聖祭(忌明け祭法要)後に贈る。
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| 前夜祭(通夜)時の教会・神父への謝礼 | 遺族 | 御ミサ料 ミサ御礼 献金 御礼 |
【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 葬送式(葬儀)時の教会・神父への謝礼 | 遺族 | ||
| 教会の使用料 (教会を借りる場合) |
遺族 | 御席料 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 神父へのお車代 (自宅で行なう場合) |
遺族 | 御車料 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 葬送式に弔慰金を贈る | 身内 身内以外 |
御花料 御霊前 |
【金封】 双銀結切り/双銀あわび結び 水引熨斗なし 【のし袋】 白無地/御花料字入 |
| 前夜祭・葬送式時の志 | 遺族 | 粗品 志 |
【のし紙】 藍銀結切り(蓮なし) 藍銀あわび結び(蓮なし) 黄白結切り/黄白あわび結び |