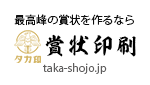行事別
【佛式】
【神式】
【キリスト教】カトリック
【キリスト教】プロテスタント
葬儀と法要のマナー
【佛式】
【神式】
【キリスト教】
慶弔用品の使い分け
一月【睦月】
二月【如月】
三月【弥生】
五月【皐月】
六月【睦月】
七月【文月】
八月【葉月】
九月【長月】
十一月【霜月】
十二月【師走】
年中
見舞
慶弔用品の使い分け
元旦・初詣
元旦(がんたん)について
元旦は年の最初の日「元日(1月1日)の朝」のことを言いますが、現在では元日そのものを表わす言葉として元旦が一般的に用いられてます。
正月の最初の日(第1日目)のことを言いますが、正月3日間のことを「元三日(がんさんにち=または、げんさんにち)=年の初めの3日間との意」といい、「旦」とは朝や明け方という意味で、「年が明けた3ヵ日の最初の日」ということを表しています。
年の初め・月の初め・日の初めであることから「三始(さんし)」とも言われます。
初詣(はつもうで)について
本来は大晦日の夜半(または元日の早朝)に、恵方参りと言って「恵方(えほう=その年の歳徳神の方角=干支により定められる)」に位置する社寺に詣でる習慣がありました。
現在では大晦日にお寺に参拝して除夜の鐘を聞いて、その足で神社に詣でる人が増えつつあるようです。
一般的には正月三ヶ日間のいずれかに、1年間の厄払いと無病息災を願って、地域の神社に詣でることが多いようです。
神社での正式な参拝の仕方
- お賽銭を賽銭箱へ投げ入れます。
- 神殿に垂れ下がっている縄紐を振って鈴を2~3回鳴らします。
- 二拝(二礼=両手を合わせたまま頭を二回下げる)・二拍手(二回柏手を打つ)・一拝(一礼=再び両手を合わせて頭を一回下げる)の順に拝礼をします。
※喪中の場合は初詣を避け、4日以降または松の内以降か小正月以降に参拝するのが良いとされています