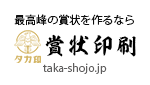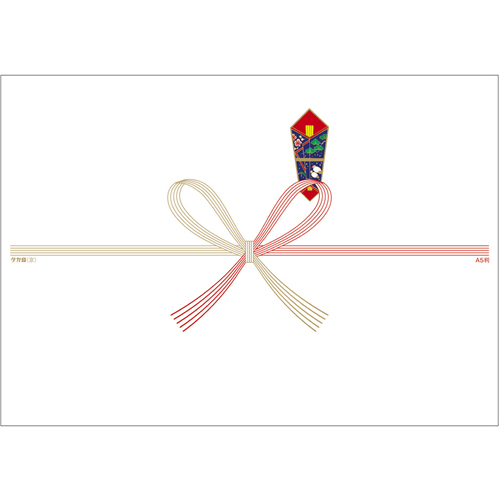お中元・暑中見舞(残暑見舞)
贈答習慣
- お中元
- 中国古来のまつりごとである上元・中元・下元の三元の内、7月15日の中元と日本古来のまつりごとの一つである7月の御霊祭における贈答習慣に加えて、伝来した佛教の7月15日に行われる盂蘭盆会とが重なったことから、お中元の贈答が盛んに行なわれるようになったようです。
- 暑中見舞い
- 暑中見舞いのご挨拶は、土用(7月19、20日~8月6、7日)の18日間に行なうのが礼儀です。御中元の贈答時期が忌中に掛かって外す場合は、この期間に暑中見舞いとして贈ります。
暑中見舞いテンプレートが無料でダウンロードできるサイトはこちら↓
暑中見舞い.com
贈答時期
- お中元
- 関東地方では新暦で行うことから7月初めより中頃までに、関西地方では旧暦で行うことから1ヶ月遅れの8月初めより中頃までに贈るのが一般的です。
- 暑中見舞い
- 土用の内に贈ります。尚、立秋(8月7、8日)が過ぎたら「残暑見舞い」になりますので注意が必要です。暑中見舞いの「はがき」などの挨拶文も同様です。
お返しの次期
- お中元
- お互いに贈りあうことがお返しになり、また習慣ともなっています。 お中元返しをしない場合は、届いたその日の内に電話や礼状で感謝の気持ちを伝えるようにします。
- 暑中見舞い
- お見舞いを受けたら、その日の内に先ず一言お礼の電話か礼状を送ります。気になる方にはお見舞い返しとして御礼を、訪問を受けた場合も御礼の手土産を差し上げるのが礼儀です。
ひとくちMEMO
- 東日本では7月初めより中頃までの間に中元を贈る。それ以降は暑中見舞いにて贈る。西日本では1ヶ月遅れの8月初めより中頃までの間に贈る。特にお返しの必要はないが電話か手紙でお礼の心を伝える。気がすまない場合はお中元を贈るのもよい。当方又は先方が喪中の場合でも、お中元を贈ることに差し支えはないが、忌中(忌明け祭前)の場合や気になる場合は、時期をずらして暑中見舞い(立秋まで)や残暑見舞い(立秋以降)の形で贈るのもよい。
- 古く中国から伝わった三元と称して、贖罪(代償物によって過去に犯した罪業をあがなうこと)の日とした上元(1月15日)・中元(7月15日)・下元(12月15日)の内の中元が、日本古来の御魂祭り(1年を2回に分けて先祖の霊を迎えてお供え物や贈り物をした習し)と、伝来した佛教の盂蘭盆会(7月15日)とが重なって、現在の中元贈答習慣が根付いた。
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| お中元を贈る | 当方 | 御中元 |  【のし紙】花結び祝 |
| 暑中見舞を贈る | 当方 | 暑中御見舞 残暑御見舞 |
お中元にふさわしい「のし紙」
お中元は、日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝える大切な風習です。上半期のお礼として贈るお中元には、選ぶ贈り物だけでなく、その贈り方にも心を配ることが大切です。その一つとして、贈り物に「のし紙」を使用することで、より丁寧な印象を与えることができます。お中元には「花結び」の水引が施されたのし紙を使用するのが一般的です。花結びは、何度でも結び直せる形状から「繰り返して喜びが訪れる」という意味を持ち、お中元のような定期的な贈り物に最適なデザインです。この水引を選ぶことで、相手への配慮を示すことができます。また、直接手渡しする場合には、「日頃のご厚情に感謝しております」といった一言を添えると、より気持ちが伝わります。遠方の方には配送を利用する場合が多いですが、その際も、のし紙が丁寧にかけられているか確認しましょう。