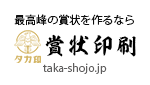行事別
【佛式】
【神式】
【キリスト教】カトリック
【キリスト教】プロテスタント
葬儀と法要のマナー
【佛式】
【神式】
【キリスト教】
慶弔用品の使い分け
一月【睦月】
二月【如月】
三月【弥生】
五月【皐月】
六月【睦月】
七月【文月】
八月【葉月】
九月【長月】
十一月【霜月】
十二月【師走】
年中
見舞
慶弔用品の使い分け
冠婚葬祭共通の回答
質問をキーワードから検索する
冠婚葬祭共通の回答一覧
- 質問:祝い用には「熨斗(のし)を付ける」のに、弔い用には「熨斗(のし)を付けない」...
- 祝い用には「熨斗(のし)を付ける」のに、弔い用には「熨斗(のし)を付けない」のは何故ですか。
- 答え
- 熨斗の起源である「伸し鮑(のしあわび)」は元々、祈願や大願成就を感謝して神社に奉納された神事のお供え物であったものが、武家の出陣や帰陣の祝膳や祝儀として用いられるようにもなり、やがては祝事や慶事の儀式に高価な贈答品として用いられるようになりました。
後には祝いの品には「祝いのお印」として伸し鮑を形ばかりに包んだものを付けるようになり、それが現在のお祝い用の慶弔用品にデザインとして用いられるようになりました。従って、熨斗はお目出度い贈答品の「お祝いのお印」であることから、弔いごと全般・傷病見舞い・災害見舞い用などの慶弔用品には付けないことになっています。
尚、鮑は元々「なまぐさ物」であることから、贈答品がお祝い用であっても「肉や魚介類=貝類・鮮魚・精肉・鰹節・卵など)」は、なまぐさ物が重なることを忌み嫌って「熨斗を付けない」ことになっています。