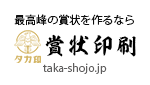行事別
【佛式】
【神式】
【キリスト教】カトリック
【キリスト教】プロテスタント
葬儀と法要のマナー
【佛式】
【神式】
【キリスト教】
慶弔用品の使い分け
一月【睦月】
二月【如月】
三月【弥生】
五月【皐月】
六月【睦月】
七月【文月】
八月【葉月】
九月【長月】
十一月【霜月】
十二月【師走】
年中
見舞
慶弔用品の使い分け
祭についての回答
質問をキーワードから検索する
祭についての回答一覧
- 質問:12月13日は「正月事始め」と言われていますが、どのような行事が行われるので...
- 12月13日は「正月事始め」と言われていますが、どのような行事が行われるのですか。
- 答え
- 正月事始めとは、新しく迎える正月に新しい年神様を迎えるための諸準備を始める最初の日とされた日で、この日より大晦日までの31日までに正月の準備を順次すすめていきます。
12月13日には、正月事始めの最初の行事である「煤払い(すすはらい)」が行われました。
昔はどこの家にも竈(かまど)や囲炉裏(いろり)があったことから、一年間に溜まった煤を取り除き家の内外を大掃除するもので、煤掃き・煤納めの行事とも言われました。
煤払いを終えた後には障子や襖の貼り替えなども行われていましたが、現在でも正月を迎える前の年末の大掃除として行われ、多くの寺院や神社などでもこの日に煤払いの行事が行われています。
古くは煤払いが終わったら、「松迎え」といって雑煮を炊くための薪や門松に使う松を山に取りに行く習慣があり、新年の年男が新年の恵方の方向にある山に出かけました。
その他にも、もちつき・門松や松飾り作り・鏡餅飾り・おせち料理作り・雑煮の用意などが各家で作られ準備されていましたが、現在ではいずれも作られたものを購入することが多くなっていることから、花柳界や芸能関係などでは正月事始めの行事として残っているものの、一般的には正月事始めの日が重要視されなくなってきています。