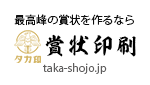行事別
【佛式】
【神式】
【キリスト教】カトリック
【キリスト教】プロテスタント
葬儀と法要のマナー
【佛式】
【神式】
【キリスト教】
慶弔用品の使い分け
一月【睦月】
二月【如月】
三月【弥生】
五月【皐月】
六月【睦月】
七月【文月】
八月【葉月】
九月【長月】
十一月【霜月】
十二月【師走】
年中
見舞
慶弔用品の使い分け
縁起物(松竹梅)
松竹梅(しょうちくばい)について
松・竹・梅は「歳寒三友」(さいかんのさんゆう)と呼んで画の題材とされていました。それから日本に伝わり、めでたいものとして慶事の象徴とされています。
「松竹梅」の順番は、おめでたいものに加わった時代の順番になっています。
・松→平安時から
・竹→室町時代から
・梅→江戸時代から
また、特にめでたく縁起の良い取り合わせとされているのが「松に鶴」「竹に雀」「梅に鴬」です。
お寿司などのランクは、特上や並と呼ぶよりも、松竹梅と示した方が美しいということで、使用されてきたそうです。
松竹梅の由来
- 松
- 常緑樹で1年中枯れることがなく、また1株に雄と雌を有することから大変めでたい樹とされ、日本では古くから神の宿る神聖な樹とされ、何十年、何百年とその姿を保つことから、「節操・長寿・不老不死」の象徴とされてきました。また、二股に分かれている葉には殺菌効果があり、今でもお祝いの食事、お赤飯などの上に飾られることがあります。
- 竹
- 常緑樹で1年中枯れることがなく、根が周囲にはびこって次々と新芽を出して広がる様は「子孫繁栄」の象徴とされてきました。節の中の水は飲み水となり、葉は薬草ともなり、筍は食用になります。竹になってからは食器・家具・建築材・楽器・玩具など多用途に役立つことから、生活に密着した貴重な植物とされてきました。
- 梅
- 苔が生える程の樹齢となっても、早春に他の花より先駆けて気高い香りをともなって美しく花を咲かせる生命力の強さから、「気高さや長寿」の象徴とされてきました。 熟すと健康に良いとされる梅酒や梅干しなどをはじめ、乾燥させて薬としても用いられたが、未熟な内に食すると中毒をおこす場合もあることから、薬にも毒にもなる木とされています。