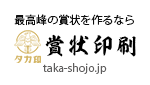縁起物(おせち料理)
おせち料理の起源
おせちの「せち」は、節句の「節」からきており、節句については日本古来から伝わる季節ごとの収穫を感謝する神事と、中国より渡来した「五節句」とが奈良時代の頃に折衷(習合)されて、公家社会における行事の一つとして根付いていったようです。
年始め(1月7日)、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の五節句などの各節に神様に供えられたお供え物を「節供=せっく」と言ったことが発祥のようですが、「おせち」はその節供の料理を「御節=おせち」と言ったのが語源のようです。元々、節供である御節(おせち)は、その季節の収穫物を供えたものですが、公家社会で行事化されるにともなって宮中料理の「おせち料理」となって、季節の収穫物中心に邪気祓いや招福・不老長寿などに通じる現在のものに近いものへと変化していったようです。
一般庶民の間に取り入れられるようになったのは江戸時代中期以降になりますが、五節句の内の1月7日の「人日の節句」が正月と折衷(習合)され、また他の節句のおせち料理も簡素化され、新年を迎える大切な行事である正月のおせち料理だけが残り現在にいたっているようです。
おせち料理の意味
祝い肴三種
これと餅を揃えれば正月が迎えられる、基本の正月料理です。献立は地域や家庭によって様々です。主に関東地方では「黒豆」「田作り」「数の子」の三種ですが、関西地方では「黒豆」が「たたき牛蒡」に変わったり「田作り」が「たたき牛蒡」に変わったりします。
 黒豆
黒豆- 一年中『まめ(真面目)』に働き『まめ(健康的)』に暮らせるようにと願いが込められている。
 数の子
数の子- 数の子には卵の数が多いことから、子孫繁栄との願いが込められている。
 田作り
田作り- 昔、田んぼの肥料としてイワシが用いられていたことから豊作を願う意味が込められています。
 たたき牛蒡
たたき牛蒡- 形や色が豊作の時に飛んでくるとされている黒い瑞鳥を連想させることから豊作を願う意味が込められています。
口取り
口取りとは「口取り肴」の略で祝儀の膳につける引出物としての料理のこと。
 紅白かまぼこ
紅白かまぼこ- 紅白は祝儀用のめでたい彩りとして使われています。
 伊達巻き
伊達巻き- 「伊達」は華やかや派手さを表しており、巻き物(書物)に似た形から知識や文化の発展を願う意味が込められています。
 栗金団(くりきんとん)
栗金団(くりきんとん)- 「金団」とは黄金の団子という意味で、豪華さを表しており見た目の色合いが金塊のように見える事から用いられている。
 昆布巻き
昆布巻き- 「よろこぶ」のごろ合わせから用いられている。
 お多福豆
お多福豆- 文字通り、多くの福を招来するという意味が込められている。
酢の物
 紅白なます
紅白なます- お祝いの水引をかたどったもので、おめでたい意味が込められている。
焼き物
 鰤(ブリ)の焼き物
鰤(ブリ)の焼き物- 鰤(ブリ)は出世魚であることから、出世を祈願するため用いられている。
 鯛(たい)の焼き物
鯛(たい)の焼き物- 「めでたい」のごろ合わせから用いられている。
 海老(エビ)の焼き物
海老(エビ)の焼き物- ひげや腰が曲がっている形が老人を連想させることから長寿の願いが込められている。
煮物(煮しめ)
 里芋
里芋- 小芋がたくさん付くことから、子宝に恵まれる願いが込められている。
 くわい
くわい- くわいは大きな芽が出ることから、出世を祈願するために用いられている。
 蓮根(れんこん)
蓮根(れんこん)- 孔が空いており先が見通せることから、未来の見通しがきくという縁起をかついだもの
 八つ頭
八つ頭- 末広がりで人の頭に立つ意味から縁起の良いものとして用いられている。
 トコブシ
トコブシ- 別名を「フクダメ」といい、福がたまるようにとの願いが込められている。