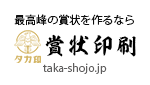行事別
【佛式】
【神式】
【キリスト教】カトリック
【キリスト教】プロテスタント
葬儀と法要のマナー
【佛式】
【神式】
【キリスト教】
慶弔用品の使い分け
一月【睦月】
二月【如月】
三月【弥生】
五月【皐月】
六月【睦月】
七月【文月】
八月【葉月】
九月【長月】
十一月【霜月】
十二月【師走】
年中
見舞
慶弔用品の使い分け
縁起物(門松)
- 目次
- 門松について
門松について
新年を祝って、正月の門前に立てる一対の松飾りことをいい、向かって左側を雄松、右側を雌松と言います。本来はその年の年神様を招き入れ、一年の厄祓いをして無病息災と招福を願うものです。
関東地方では三本の竹を松で囲った上に、裾回りに松の木を割って並べ、むしろでを巻いて荒縄で束ねたものを用いるのが一般的で、豪華なものは竹(笹)・梅の枝・南天などをあしらったものもあります。関西では幼松(根付きの小松)を半紙で巻いて金赤の水引をかけたものを用います。
年末の内に立てますが、29日は「九松(苦待=苦労を待つ)」と忌み嫌い、31日は「一夜付け=又は一夜飾り」と言って神様に対して失礼ということから、28日までに取り付けを済ますのが一般的です。
- 目次
- 門松について